
本名 益田孝 ますだたかし
法号 鈍翁 どんのう/どんおう
時代 江戸幕末/明治/大正/昭和
生没 1848〜1938
職種 実業家
職歴 陸軍→大蔵省→三井物産
出身 佐渡島(新潟県佐渡市)
もくじ
益田鈍翁の読み方は「ますだ どんおう/どんのう」
佐渡島(新潟県佐渡市)で生まれで、本名は益田孝(ますだたかし)。父の仕事で江戸へ行った鈍翁(孝)はヘボン塾で早くから英語を習得。父とともにヨーロッパも歴訪し、語学力と見聞を磨きます。帰国後は陸軍へ入りますが、明治維新の際に井上馨に才覚を認められて大蔵省へ入省。まだ若いうちにその職をしりぞき、井上馨と三井物産を創業し初代社長に就任。明治時代を牽引する実業家でした。
茶の湯は弟のひとことがきっかけ
充実した実業家人生を歩んでいた鈍翁が茶の湯をはじめたのは40才のころ。
鈍翁が勤めている三井家は代々茶の湯をたしなむ一家ですが、それを知った鈍翁の弟が
「美術品の収集はするのに、なぜ茶の湯をしないのか」とすすめたのがきっかけです。
その後、表千家不白流にて茶の湯をはじめます。
鈍翁の名前の由来は茶碗「鈍太郎」
鈍翁の名前の由来は、明治40年頃に、表千家6代目家元・覚々斎(かくかくさい)の手作りの黒楽茶碗「鈍太郎」を手にしたことによります。その茶碗を気に入り、「鈍」の字と「翁」を組み合わせて「鈍翁」とし、品川の御殿山に茶席を立てた時も「太郎庵」の名前をつけました。
茶会「大師会」の創設者
現代にも続く茶会を創設したことも鈍翁の功績の一つです。名高い実業家や著名人を招き、空海(弘法大師)追悼と古美術の鑑賞を目的に大師会を開催。招かれること自体がステータスとなるほど有名な茶会になりました。また、京都の光悦寺で開催される光悦会や、名古屋の敬和会の誕生にも一役買っていたようです。
益田鈍翁1848~1938年と同時代のひと・もの・こと
同世代のひと
裏千家
11代 玄々斎(げんげんさい)
1810〜1877年
12代 又玅斎(ゆうみょうさい)
1852〜1917年
日本
小林清親(こばやし きよちか/浮世絵)
1847〜1915年
下村観山(しもむらかんざん/日本画)
1873〜1930年
岡田三郎助(おかだ さぶろうすけ/洋画)
1869〜1939年
世界
チャイコフスキー(音楽家)
1840〜1893年
ドヴォルザーク(音楽家)
1841〜1904年
モネ(画家)
1840〜1926年
ゴーギャン
1848〜1903年
同世代のできごと
日本
1867年 王政復古の大号令
1871年 廃藩置県
1889年 大日本帝国憲法を発布
1925年 普通選挙法が成立
世界
1869年 スエズ運河が開通
1911年 (清)辛亥革命
1917年 (露)ロシア革命
1922年 (露)ソ連が成立
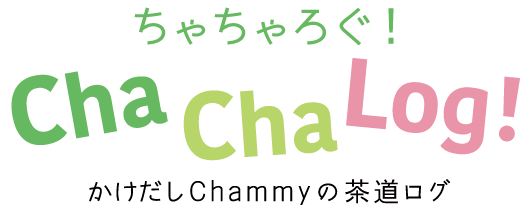
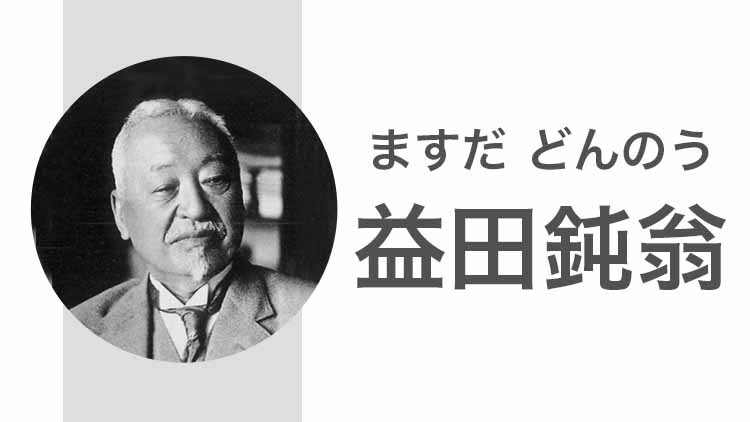

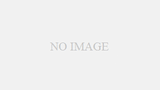
コメント