もくじ
古帛紗など茶道具を見るのに覚えたい色名
はじめに覚えておきたい青
| はなだ | |||
| 縹 | |||
| 藍と黄檗で染める。かつては露草の花の汁で青く染めていたため、花田とも書かれる。 | |||
| あい | |||
| 藍 | |||
| インディゴブルー。藍は世界各地で栽培されており、日本では蓼藍で染色をする。 | |||
| こん | |||
| 紺 | |||
| 藍染めの中でもっとも深い色。染色を繰り返し、もう染らなくなった色は上紺、留紺と呼ばれた。 | |||
鮮やかな緑色
| もえぎ | |||
| 萌葱 | |||
| 芽が出たネギの青々とした様子から付けられた名前 | |||
| あさぎ | |||
| 浅葱 | |||
| 平安時代からある伝統色で、ねぎの葉の色からとられた名前。 | |||
| もえぎ | |||
| 萌黄 | |||
| 芽吹きはじめた若葉のみずみずしい色合いのこと。萌木とも。 | |||
花の名前が多いむらさき
| ふじむらさき | |||
| 藤紫 | |||
| 藤の花を連想させる色。江戸時代の後期から見られる色で「紫藤」の名前でも知られる。見頃は4〜5月で、春の季語とされる。 | |||
| あやめ | |||
| 菖蒲 | |||
| しょうぶと読むが、中世の日本ではあやめと読む。乾燥した陸地を好んで咲く。 | |||
| かきつばた | |||
| 杜若 | |||
| 水辺に葉をのばして咲く。花弁の中央に一筋だけ白色が伸びる。 | |||
やわらかな赤
| ちょうしゅん | |||
| 長春 | |||
| 庚申薔薇(こうしんばら)という中国原産のバラの漢名が「長春花」。意味は常春。 | |||
| えんじ | |||
| 臙脂 | |||
| コルチニールや貝殻虫を染料とする。 | |||
| すおう | |||
| 蘇芳 | |||
| 熱帯地方の落葉樹である蘇芳の幹の芯を煎じて染色することから。紅花や茜の赤の代わりとして使われている。 | |||
発色の良いオレンジ
| しゅ | |||
| 朱 | |||
| 天然顔料の辰砂から染色すると本朱と呼ばれ、のちに、硫黄と水銀で作られると銀朱(バーミリオン)と区別された。 | |||
| だいだい | |||
| 橙 | |||
| お正月の鏡餅に飾るダイダイの実から取られた名前。 | |||
| おうに | |||
| 黄丹 | |||
| クチナシと紅花で染める。飛鳥・奈良時代には皇太子の位色として、他の人は着られない色だった。 | |||
淡い色合いの茶色
| きんちゃ | |||
| 金茶 | |||
| 江戸時代に書かれた『当世染物鑑』という書物に登場する名前。ヤマモモの木の樹皮とヤシャブシの果実などを使い染めていた。 | |||
| しらちゃ | |||
| 白茶 | |||
| 江戸時代の流行色で赤みがかったものや、黄色が強いものなど幅がある。元禄中期には濃い色の白茶が流行し、徐々に薄い色が茶人や寄好者の好みであると変化していく。 | |||
| たいしゃ | |||
| 代赭 | |||
| 赭(そほ)という顔料に使われる赤土の有名な産地が唐の代州だったことから、代赭となる。唐の代州は現在の山西省のあたり、中国の真ん中右上。天然の赭土を水にいれて上澄みを精製する。 | |||
茶人の名前がついた色
| りきゅうちゃ | |||
| 利休茶 | |||
| 茶人利休にあやかって付けられたとされる名前。色は江戸時代の中期以降から登場。 | |||
| りきゅうしろちゃ | |||
| 利休白茶 | |||
| こちらも利休の名前にあやかって付けられた色名。 | |||
| えんしゅうちゃ | |||
| 遠州茶 | |||
| 武家茶道遠州流の開祖の小堀遠州が好んだとされる色。造園事業などで活躍した大名。 | |||
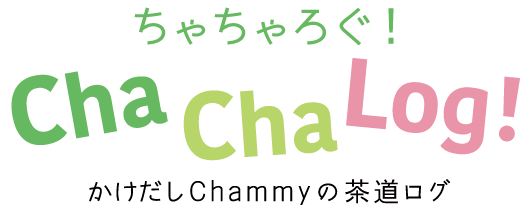

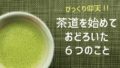

コメント